
MENU
かつては駄菓子屋でも売られていた静岡のソウルフード“静岡おでん”。
ほか数々の静岡グルメを提供するのは、東京・高田馬場にある「静岡おでん ガッツ」。
静岡での食べ方を再現したいと語る静岡出身の店主・市川徳二さんに、
お店のこと、そして静岡に対する並々ならぬ想いを伺います。
―「静岡おでん ガッツ」のこだわりをぜひ教えてください。
なるべく静岡で作られたものや静岡産の原材料、調味料を使うことですね。
あとは、静岡の人たちが食べているような食べ方や調味料の使い方、調理の仕方を再現すること。
極端なことを言うと、料理の質とか美味しさ、値段っていうよりも、
どれだけ静岡の日常に近いものを提供できるかということを目指しています。
たとえば…はんぺんフライは、もしかしたらマヨネーズやお醤油で食べたほうが美味しいかもしれない、
でも自分が子どものころは中濃ソースで食べるのが絶対で、自分の中でそれが慣れ親しんだ味。
美味しいよりも、あえて昔ながらの静岡県人の食べ方で食す。
そういうところにはこだわりたいと思っています。

―なぜ静岡おでんのお店を開店しようと?
私の実家は酒屋をやりながら軒先で酒やつまみを提供する、いわゆる角打ちのような店をやっていました。
父の作ったおでんをお客様に提供していて、私も小さい頃からそれを食べてという環境で育ちました。
東京の大学に進学、就職した中で気付いたのは、父への想いと静岡に対する想い。こと静岡に対する想いは
他者より秀でているんじゃないかと。その想いを形にすべく、2012年に開店しました。
―お父様が30年以上作られてきた「正統派ストロングスタイルの静岡おでん」とは?
静岡おでんにはいろいろな定義があって。たとえば黒はんぺんがあるとか、
青のり・だし粉をかけて食べるとか、串に刺してあるとか。それをきちんと踏襲しているってことですね。
利益を追究すれば、どうしても食材や調理法、提供方法を変えたりすることが出てくるのですが、
うちは改変せず、本当の静岡のおでん屋さんで出しているようなおでん。
それに限りなく近いものを提供したいと。
―意識されているのは「ザ・静岡」の味や体験ということでしょうか。
目指したいのは、ただの飲食店というより、もう少しエンターテインメント性の高いところ。
目標としてはディズニーランドみたいな、「静岡」っていうテーマパークに来たような
フワフワした気持ちになれるといいかなと思って。
気軽に来て、静岡の空気感を感じていただければ、それでいいと。
あんまり大それた期待をもってうちの店に来ていただくよりも、
たまたまフラッと入って2、3杯飲んで1000円、2000円使って楽しく過ごしてもらえら、
それがこの店の役割だなと思うんですよ。

―市川さんの静岡に対する想いを強く感じます。
やはり静岡のためになるようなことをしたいですよね。
うちは静岡ありきの店で、静岡からいろいろなものをいただいている。
その分きちんと恩返しをしない限りは、当店の発展はないと思いますから。
感謝の気持ちを、静岡の未来のために何か尽力することで示せたらと。
静岡の美味しいもの、温かい文化に観光地。そういう良さを東京で発信して、静岡に関心を向けていただいて、
そこから実際に静岡に出かけ、さらには「ここに住んでみたい」と思っていただけるような…。
そういう演出ができたらなとは思いますね。
―やはりお客様とも静岡の話題になることが多いとか。
おすすめの旅程や食べ物の話だけじゃなく、静岡で暮らしてみたいっていう話になることもあるんです。
地元は静岡ではないけれど、将来的には静岡に移住して清水エスパルスを
もっと応援したいんだっていう方、実は結構いらっしゃるんですよね。
―そこまで熱心なサポーターさんが多いんですね! 驚きました。
静岡は気候的にも温暖で、静岡市の中部地区は雪も降らない。
大都市圏からほどよい位置にあるということもあって過ごしやすい。
海があって山があって、美味しいものがたくさんあって。
そんなに刺激的なものはないかもしれませんが、毎日を心穏やかに過ごすのに
一番適している場所だなと思うんですよね。
温泉もあるから、静岡という場所がものすごく極楽の場所になっていくんじゃないかなって思います。
―刺激が欲しいときは大都市圏に行けばいいわけで、そう考えると静岡は非常に暮らしやすい場所だと。
そう。ありきたりの表現しかできないんですが、とにかく暮らしやすい。
それがすべてなんですよね。良いところだから絶対に気に入りますよ、と。
それは私の中で絶対的すぎて揺るがない。
もしかしたら仕事をするという点ではまだ難しいかもしれませんが、
人として生活するということにおいては、多分日本の中でも一番良い場所なんじゃないかな。
ライター:左藤緋美
「川根茶」は静岡が生んだ日本三大銘茶のひとつ。
この販売促進のため、静岡県中部の山間に位置する川根町と川根本町エリアで
生まれたのが「川根お茶街道推進協議会」です。当協議会で川根茶の普及に努める花房則告さんに、
川根茶、そして川根茶を生み出した山里、川根本町の魅力についてお聞きしました。
―「川根お茶街道推進協議会」の活動について教えてください。
「川根茶を広めたい」という共通の想いを胸に、役場や農協、観光協会や各市町の商工会など
計12の団体が参加し、川根茶の販売促進のために活動しています。
具体的には、毎年11月23日に開催されているイベント「川根時間」への参加。
これは川根の紅葉、自然とともに、町の施設で川根茶をゆっくり楽しんでいただくもので、
お茶の手揉み体験や品評会の上位入賞茶体験などもできる体験イベントになっています。
町で採れた最初のお茶を奉納し、お茶の安全祈願をする「献茶式」や「新茶の初取引」にも参加したり、
「川根茶の日」と制定されている4月21日を中心にイベントを開催していくなど、
川根茶の普及に日々努めています。

―後継者や若い世代に向けてのアプローチもなさっていますね。
お茶に関する勉強の場「川根茶塾」を実施して、
茶商の若い後継者の方を集めて経営の仕方を勉強していただいたり、お茶を使った料理の試作をし、
実際に町の方に食べていただいたり。また、小さい頃から川根茶に慣れ親しんでもらいたいと、
茶業青年団が「お茶の入れ方教室」を各市町の小中学校で開催しています。
ここ最近は関東方面に出向き、実際に川根茶を飲んでいただく機会をつくる活動へとシフトしていますね。

―川根茶の魅力とは、どういった点にあるのでしょうか。
お茶には「深蒸し茶」「浅蒸し茶」があって、川根茶は主に、
茶葉のリーフの形状がしっかりした「浅蒸し茶」が中心なんですね。
全国茶品評会で昨年度も農林水産大臣賞を受賞したり、出品された方がすべて3位以内に入賞したりと、
高品質な点が川根茶の特徴かつ魅力だと思います。
川根茶は山間部で採れるので、他の産地より採れる量が少なくなってしまう。
であれば「量より質」で勝負しようと、品質に力を入れているというわけです。
―川根茶を初めて飲まれた方から、どういった感想を聞くことが多いでしょうか?
浅蒸しの、濃緑の針のような茶葉を見て、「わぁ…!」と驚かれる方が多いですね。
飲んでいただくと「深蒸しよりも渋味が感じられる」というお声が聞かれます。
川根茶には、嫌味のない渋味があるのが特徴。
渋味もあんまり強いと嫌われてしまいますが、それぞれの茶商独自の仕上げ方によって、
いい塩梅の渋味が感じられるんですよ。
浅蒸し茶はお茶の色としてはかなり薄いものの、味は濃く強く感じられる。
若い方にぜひ川根茶のコクを知っていただけたらと思いますね。
―浅蒸し茶、ぜひ飲んでみたいと感じました! 川根茶をまだご存じない方も多いとのことですが。
全国的にみると、川根茶は流通する量自体が少ないですからね。
特に若い方に向けて発信していかなければということで、
手軽に飲める「川根茶ペットボトル」を2022年に発売しました。
他のペットボトル茶との差別化を考えたとき、通常は二番茶、秋冬番茶を使うところを、
うちは一番茶で勝負しようと。1本200円と少々割高かと思いつつ、
飲んでいただいた方からは「もっと高くてもいいんじゃないか」とのお声をいただけて…。

―実際に飲まれた方が、一番茶の美味しさや価値を実感されているということですね!
嬉しいですね。川根地域や隣の市町での限定販売で、現在2万本以上出荷。
今後は県内外の方にも飲んでいただけるようPRして、
ゆくゆくはお茶の葉からお茶を入れていただけるようになれば…と思います。

―日本三大銘茶のひとつを生んだ川根エリア。魅力はなんでしょうか?
水や空気はもちろんですが、夜の星空がもう本当に綺麗なんです!
無数の星たちが光り輝く星空が、視界いっぱいに広がるのが一番の魅力。
ご覧になった方は驚かれます。自然環境が豊かで、エメラルドグリーンの水を
たたえる接岨湖や12カ所以上あるつり橋など、挙げればきりがないほど。
都会から来た方々にもとことん付き合うといった、
人情味にあふれた方々が多いのも魅力ではないでしょうか。
―ここ最近、都会から移り住む若い方が増えたとお聞きしました。
カフェやフランス料理店を開かれる方も多くて、町の雰囲気もずいぶん変わってきました。
こうして、移住される若い方々と一緒になって町を盛り上げていけているのが
とっても嬉しいんですよね!
同時にお茶が中心の町でもありますので、「美味しいお茶づくりにご興味のある方は、
お茶の木を育てるところから始めてみませんか?」と伝えたい。
バックアップする環境は揃っているので、お茶づくりに関心のある方はぜひ、お越しいただきたいですね。
TEXT/左藤緋美
小川港と焼津港、二つの漁港をもつ焼津市は、日本一の水揚高を誇る水産都市。
その焼津には、京都や大阪の高級料亭から鯖寿司や〆鯖の注文が絶えない加工会社「焼津冷蔵」があります。
「ヤキレイ」として一般の方向けに通販事業も始めた3代目社長・原崎太輔さんに、
そのこだわりや水産都市・焼津についてお聞きしました。
―焼津冷蔵さんは、高級料亭や百貨店などに鯖寿司や〆鯖を卸していると聞きました。
生食用の鯖の加工品が主力商品で、もともと出荷先はほとんどが鯖寿司屋。
我々が作っている塩鯖は鮮度も品質も非常に高く、
「焼津の塩鯖だったら生で食べられる」と高評価をいただいたんです。
こうして、多くのブランドや料亭の鯖寿司のもとになる〆鯖を作り出したのが20~30年前。
おかげさまで、京都、大阪の駅で販売されている鯖寿司の多くを
当社が手掛けさせていただいて、今や抱えるレシピは200超になりました。

―そんなにも! 焼津の〆鯖は関西圏でブランド認知されているというわけですね。
でも静岡の方は意外とご存じない。やはり地元の方にも知っていただく、
召し上がっていただくというのは我々がやらなければいけないことだと思っています。
そこで当社でも一般の方向けに約2年前から、京都や関西のお客様の競合にならないよう
通販等の直売スタイルでの販売をスタートさせました。
―内閣総理大臣賞受賞「切れてるお茶しめさば」には、なんとお茶が使われているとか。
臭い消しのためにお茶で下処理をしているんです。
スーパーで売る〆鯖はパック入りで賞味期限も長く、そのため鯖の臭いが出やすい。
だからといって添加物はあまり使いたくない。そんなときにお茶のカテキンが臭い消しに効くと知り、
静岡のお茶で下処理することを考えついたんです。
お茶の緑色が鯖の身に残ってしまうのが難点だったのですが、
緑茶の一種「サンルージュ」は淡いピンク色になることに数年がかりで辿り着いて…。
その後は品評会などでも認められ、内閣総理大臣賞を受賞することができ、
伊勢神宮にも奉納させていただきました。
今は一般的な緑茶でも緑色が残らない製法を社員が考えてくれて、
ゆくゆくは生産農家の方と組んだりできると面白いなと思っているところです。

―鰻の蒲焼にも、お茶から着想した「深蒸し」という製法を取り入れていらっしゃいますね。
箸でなかなかつかめない柔らかい蒲焼を作るのがこだわり。
お茶の深蒸しにヒントを得て、約2倍の時間をかけて蒸すんです。
すると、柔らかさと一緒に本来持っているコクも出る。
鰻はよく火入れすると美味しくなるものの、驚くほど縮むので、
深蒸しをやる工場はあまりないんじゃないかな…。
よく、食べる前にフライパンで蒸すとお店の味に近くなるとか言いますが、
それは当社の蒲焼では絶対にやっちゃだめ(笑)。もう十分に火を入れているから、
逆に美味しくなくなるんですよ。
柔らかく美味しく食べてもらうために、しっかり火を入れる。
当社はそれをただただ真面目にやるだけ。そのぶん手間がかかるので、
お客様からは「やっぱヤキレイの蒲焼は美味しいよね、高いけどね」って言われるんですけど(笑)。

―鯖と鰻を扱うことになった経緯は?
祖父がその昔、漁師に漁船を提供する船元で、漁師でもあったのが発端です。
約50年前の駿河湾では鯖がたくさん捕れていたんですが、同時期に浜名湖で鰻の養殖が始まり、
小さい鯖をエサにするとわかった。ならば大きい鯖は人間に、小さい鯖は鰻にあげればちょうどいい、
いっそのこと鰻の養殖をと、祖父の代で考えついた。その流れで、鯖を軸に鰻も扱っているわけなんです。
―焼津市は「小川港さば祭り」が行われるだけあって、もともと鯖の水揚が日本一だったと。
そうです。でも温暖化の影響で魚が捕れる漁港がどんどん北上しているのと、
水産業自体が落ち込んできている。
ただ、今でも焼津は日本一の水揚高を誇る水産都市。
夕方になると鰹節の香りが漂ってくるディープな街ですが(笑)、
そこに根付いた会社があって、雇用を生み出し、魚で飯を食っている人間がいるということを
次の世代にも残していきたいと思うんです。

―水産業と焼津への並々ならぬ想いを感じます。「焼津冷蔵」の今後についてもお聞かせください。
「焼津にはヤキレイがあるよね」って言われるような会社にしていかないといけない。
できれば、祖父がやっていた6次産業化も目指したい。
自ら捕ってきたものを、自らが売って直接食べてもらうところまでができる会社にしたいですよね。
そこにきっと人や物が集まってくると思うんですよ。地域産業が発展すること―。
当社がそのパズルのひとつになれれば嬉しいなってすごく思います。
まずはとにかく一度、うちの〆鯖を召し上がってみてください!(笑) 本当に美味しいですから。

ライター:左藤緋美
藤枝市のお茶産業を途絶えさせまいと、茶商6社、生産農家1社がタッグを組み生まれたのが、
藤枝市を拠点に活動する「TEA SEVEN」です。
国内にとどまらず、海外への販路拡大を視野に入れチャレンジし続ける若き茶商のひとり、
小野慎太郎さんの、お茶産業、そして藤枝に対する想いとは―。
―「TEA SEVEN」で取扱いのある「藤枝かおり」は、藤枝市で誕生した新品種のお茶だそうですね。
「藤枝かおり」は、日本で藤枝市にしか植わっていない茶の木。
この木からはジャスミンのような香りがするんですよ。これを普及させたい!という想いから、
4種の商品(煎茶、抹茶玄米茶、紅茶、玄米焙茶)を誕生させました。
バリエーションを持たせたのは、煎茶が好き、紅茶が好き…というさまざまな方の好みに合うように。
大変だったのは、この品種の独自性であるジャスミン香を消さない作り方を模索したところでしょうか。
ですが、「TEA SEVEN」は茶商の集まり。ブレンド技術や玄米の割合、
茶葉の焙煎加減などはプロですから、それぞれに委ねています。
人気のサブスクサービスは6社の茶商ごとに焙煎度合いの違いや特徴が出るので、
毎月違うスタイルのお茶が味わえて面白いですよ。

―そもそも「TEA SEVEN」とはどういった形態で活動されているんでしょうか?
後継者不足、荒廃茶園が増えているという現状を鑑みて、
「藤枝かおり」の販売を海外にも拡大していこうと、
6社の茶商と1社の生産農家が集まってできた団体です。
特徴的なのは、この生産農家は有機栽培を最初に行った茶農家であること、
そして6社の茶商については、茶の鑑定技術がものすごく優れていること。
プロの茶鑑定大会「全国茶審査技術競技大会」では何度も全国大会に行っているメンバーで、
多くが段の保有者です。そのため安心安全なのはもちろん、美味しいお茶を提供できるのが強み。
主にオンラインショップと、年間150万人が訪れる蓮華寺公園内にある、
和洋折衷な青いとんがり屋根が特徴の「とんがりぼう」(旧藤枝製茶貿易商館)で販売を行っています。

―なぜ、7社協同というスタイルに?
茶商は古くからあって、昔からライバルというか切磋琢磨してきた分、
協同で一緒に何かをすることができない業種だったんです。
でも私自身、協同という意識がどこかにあったんだと思うんですよね。
日本のマーケットも小さくなっていて、販路を海外にも向けたいという中では、
規模的に小さな問屋が個々でやっていても難しいですから。
あるとき地元で、一般の参加者100名ほどを集めて“利き茶ナンバーワン”を決めるコンテスト
「天下一闘茶会」の運営を主導したのですが、こんな大きなイベントができるのであれ
ば茶商の概念を覆して協同でやっていこう、販売流通も拡大していこうと20社ほどの茶商に声をかけて。
あとさき考えずに「やりましょう!」と言ってくれたのが、私を除く6社だったわけです(笑)。
―海外を視野に入れた同志7名が集って、「TEA SEVEN」が誕生したと。
海外展開でいうと、約5年前に藤枝市と台湾の企業が包括連携協定を結んだのをきっかけに、
台湾に向け販路を拡大中です。多いときで年4~5回は台湾に渡り、PR活動を行っているところです。
直近では、2017年から続くパリ唯一の日本茶コンクール「ジャパニーズティー・セレクション・パリ」にて、
200超の日本茶の中から藤枝かおりの玄米焙茶が銅賞を受賞するという朗報もありました。
―海外でも日本茶、藤枝茶が広く認知される嬉しいニュースです! では今後の抱負は?
藤枝市の茶園面積がどんどん増えて、生産の面でも後継者が出てきて…という青写真を描いていて。
ただそのためには、藤枝茶のブランド価値が認知され、
安くない価格で販売できるのが一番じゃないかと思うんですよね。
価値を上げるべく引き続き海外展開を視野に入れて、まずは台湾での地盤固めに力を注ぎたいなと。
今年で5年目となる「TEA SEVEN」をこの先も続けていけるよう、頑張りたいですね。

―藤枝かおりの木が日本で唯一育つという藤枝市。どんな街なんでしょうか。
お茶に関する面白い文化に「朝ラーメン」があります。茶商の取引は朝4時、5時と、ものすごく早い。
生産農家や問屋の方が、仕入れが終わったあとにラーメンを食べたことから、
藤枝は「朝ラーメン発祥の地」と言われています。
ほかにも、茶農家の5月は収穫時期で多忙なので、
3月の雛祭りの際に、端午の節句のお祝いも一緒にやってしまうんですよ。
藤枝はこうした茶農家ならではの風習が残っている地域でもあります。
行政も力を入れているからか移住される方も珍しくないですが、
穏やかでゆったりした時間が流れているのが藤枝市。
そこはこれからも変わらないでいてほしいですね。

ライター:左藤緋美
伝統工芸のイメージとは一線を画す洗練された雰囲気が漂うのは、
ものづくりの街・静岡が有する日本最大級の伝統工芸体験施設「駿府の工房 匠宿」。
2021年のリニューアル以降、「匠宿」の広報・松本宏予さんに、
「匠宿」のこれまで、いま、そしてこれからについて教えていただきました。
―「匠宿」ではどういった伝統工芸が体験できるのでしょうか。
静岡が誇る伝統工芸の体験を多く取り揃えています。
駿河竹千筋細工や染め物、釘を使わず組み立てる木工指物、漆や陶芸などですね。
体験だけでなく、伝統工芸が職人から直接学べる教室も展開していて。
職人の技術に直接触れられる、貴重な機会なんじゃないかなと思います。

―体験できる作品がモダンだったり、3つある工房の工房長も若手だったりと、伝統工芸が少し身近に感じられる気がします。
若手の職人が伝統工芸を教えることで、若いファミリー層の方にもより親近感といいますか、
伝統工芸へのハードルが下がる気がしています。
人気テキスタイルブランド ”ミナ ペルホネン” との染めのコラボも、様々な層の方に喜んで頂いています。
作品の内容は、季節の行事に添ったものも含め、職人や各工房のスタッフから
どんどん新しいアイデアが上がってきます。一度来られた方が
何度でも楽しんでいただけることを念頭に置いて、
毎月何かしら目新しい体験ができるようにしています。

―2021年のリニューアルで、伝統工芸の技を用いた内装となっているんですね。
カフェの照明やのれんなどの設えにも工芸品を使用しているので、
随所に匠の技を感じていただけるのではないかと思います。
施設周辺は三方山に囲まれ、古き良き景観が残っているのですが、
その街並みにも溶け込むような建築になっていて。
現状維持ではなく良いものをどんどん取り入れていく。
だからいつもどこかしらが工事中だったりするのですが、
常に変化を続けているのでお客さまもスタッフも
飽きないのではないかと思いますね(笑)。
―施設内に静岡醸造の醸造所があるんですね! とても面白いと感じました。
静岡はクラフトビールの醸造所が多いことでも知られていますが、この丸子地区には醸造所がない。
そこで静岡醸造さんを誘致して、敷地内に醸造所を構えていただきました。
この4月にオープンしたカフェ「The COFFEE ROASTER」では、
できたての生ビールも飲むことができますよ。

―またひとつ、魅力が追加されたわけですね!
工芸品に触れるのと同時に、食を楽しめる施設でもあるんです。
いま敷地内にあるのは、静岡醸造の醸造所に、
地元で採れるハチミツや食材を使ったカフェ「HACHI & MITSU」、
あらたに加わったコーヒーの焙煎士がいるカフェ「The COFFEE ROASTER」に、
地元で愛されてきた名店『吾作』の味を継承したきんつば屋「蓬きんつば ときや」。
伝統工芸とあわせて、食の分野のものづくりについても意識しているんですよね。
ここ「匠宿」には「食の匠」もいる、と。
実際、「HACHI & MITSU」のモーニングやランチを
楽しむ目的で来てくださる地元の方も多くて!
今後フードメニューがパワーアップしていきますので、ぜひこちらも楽しみにしていただきたいですね。

―伝統工芸の体験だけでなく、世代や性別を問わずいろんな楽しみ方ができるわけですね。
「匠宿」は、いつ来ても誰と来ても必ずハマるものがある。
天候に左右されず、一日中いろんな過ごし方ができる。そんな場所なんです。
さらに施設周辺の泉ヶ谷地区は、小さな宿場町だった丸子宿の中でも、
歴史を感じる史跡や古民家とモダンなお店が同居する里山地区。
「匠宿」での伝統工芸体験を2~3つ組み合わせてどっぷり体験したあとは、
たっぷり美味しいものを食べ、ゆったり街歩きをして泉ヶ谷地区を満喫していただくのがおすすめです!
―今後の展開については?
”日本最大級”から、”日本一の”体験施設へ。体験のクオリティはもちろん、
センスや接客の良さなどすべてにおいて、これは関わるスタッフ全員が本気で目指しています。
そして“泉ヶ谷”という名前を聞いた人全員が、あの素敵な里山ね、
歴史に触れたり伝統工芸に触れたりできるところだよね、ってピンとくるような、
街全体、施設全体でそんな場所になっていくといいですね。
ライター:左藤緋美
10年ほど前に暮らしていたカナダ・バンクーバーで、
ひょんなことからクラフトビールの世界に足を踏み入れた草場達也さん。
インポーター(輸入業者)かつ、クラフトビール専門店「Beer OWLE(ビア アウル)」の
オーナーでもある草場さんが感じる、静岡のクラフトビールと街の魅力とは-。
―「Beer OWLE」で扱うクラフトビールは、常に100種類以上(!)と聞きました。
「Beer OWLE」は、クラフトビールのインポーターである当社(BC BEER TRADING)の直営酒屋です。
その強みを生かして、日本では当社としか取引のないカナダ・ブリティッシュコロンビア州や
海外の珍しい銘柄も手に取っていただけるのですが、一番大事なのは、
さまざまな品揃えがあって地元の方が手に入れたい商品があることなんです。
―地元に根付いた専門店でありたい、と。
極端なことを言えば、当社が買い付けた銘柄が並ばなくてもいい、とも思っています。
もちろん、注目度の高いスタイル、今なら「Hazy IPA(ヘイジー・アイピーエー)」や
「サワービール」も置きますが、なるべくスタイルも偏らず、
初心者からツウな方までが欲しているビールを置きたい。
そして、黙っていても売れるビールより、「これは売らなきゃいけないな」と
駆り立てられるビールを売っていきたいですよね。

―それはどういったビールなんでしょう…?
質の良さプラス、“醸造所の想いが強いビール”です。
一回のできあがりが100ケースにも満たない小さな醸造所から「この店に置きたい」と言っていただけたら、
それはもう「頑張って売りたい!」って思いますよね。
醸造所はビールを作るのが仕事で、それを流通させるのは我々の役目。
「Beer OWLE」がTシャツやキャップといったアパレルも展開しているのは、
人を呼ぶためのキャッチアップのひとつでもあるんです。
そうして来ていただいたお客様には、オートメーションじゃないサービスを提供したい。
そこは大切にしています。

―では、草場さんにとっての「静岡のクラフトビールの特徴や魅力」というと?
静岡は全国的に見ても醸造所の数も多く、質も非常に高いと言えますね。
静岡には、トップランナーで居続けている「ベアード ビール」に、
数年前にできた「WEST COAST BREWING」といった、古参から新鋭までがちゃんと揃っているのも魅力。
文脈がしっかりあって、クラフトビールの文化が醸成されてきているように思います。
都市部に醸造所があることで、ビールやその作り手のことを身近で見たり感じたりもできて、
それが味にも直結していく。これってすごく面白いことなのかなと感じますね。
―クラフトビールを愛してやまない草場さんですが、インポーターになったきっかけは?
それが…もともとはまったく別の仕事でカナダのバンクーバーに滞在していて、
のちに当社を一緒に立ち上げた塚田とはそこで出会ったんです。
彼は今バンクーバーで醸造士をやっていますが、当時は勉強のために
ホームブルーイング(家庭でのビール醸造)をしていて、「作ったら捨てる」と言う。
それならと、3日に一度のペースで貰いにいくようになって…。
とにかくとても美味しくて、これが日本でも飲めたら!と思ったのが大きかったですね。
―あまりの美味しさに、ブルワリーに通い詰めたそうですね!
当時はクラフトビールのブルワリーにアジア人がいること自体が珍しい。
なんだあいつは?と話題になったらしく(笑)、結果、ブルワリー関係者と仲良くなったり、
帰国後は別案件でインポーターとして指名を受けたりと、クラフトビールとの縁が深まっていったんです。
ビールを作りたい、広めたいという人が多い中、仕事にするというよりも、
ただ飲んでいただけの身としてはちょっと申し訳ない気持ちがありつつも、それを払拭すべく、
とにかくひたすら勉強を重ねました。
いま業界内で“それなりに詳しい奴”として見てもらえていることは…よかったな、という想いでいますね。

―海外や都心での暮らしを経て、静岡は草場さんの目にどのように映っていますか?
心地よさを感じていたバンクーバー同様、海と山がある。
そこに都市機能もちゃんとあるのが静岡。そういう地域は、地場産業が元気なんです。
資源があるから、そこにいる人たちもエネルギーのある方が多くて、特色のある方もいる。
経済合理性がなくてもここに住みたいと思える街で、これは都心暮らしでは得られなかった想いですね。
東京や名古屋、大阪にも行きやすく、何気なく入ったお店の昼食がすごくおいしいっていう(笑)。
ぜひ何も考えずに、ふらっと遊びに来てほしい。静岡はそんな場所です。
―今後の展開もお聞かせください。
静岡市のビールサプライヤーを集めた当社企画のフェスを、開催予定です。
専門店ではなくてもクラフトビールが買える。
それを実現するためには、流通業者としてまだまだやるべきことがたくさんあるなと思っています。
ライター:左藤緋美
「銀の山」のアロマが伝える、島田の豊かな風景とそこに住む人のあたたかさ
”島田の逸品”にも認定された「銀の山」のアロマスプレー。
主に島田市で採れる、廃棄予定の柑橘や木材などを原料にしたサステナブルな商品です。
その香りは、島田の豊かな風景にインスパイアされて生まれるのだとか。
島田への愛があふれる、代表の希代智子さんにお話を伺いました。

―「ほのぼの」「きよらか」「そよそよ」…。商品のネーミングがとても印象的です。
島田市に住む方々はとても親しみやすく、ほんわかしている人が多いなと感じて。
だから最初に香りを作るときに浮かんだのは、“ほのぼの”という言葉と、島田で採れる柑橘でした。
あたたかくて、移住者にも優しくて、世代を問わずそこに住む方々が安心してつながっていけるのが島田。
そんな皆さんが笑顔になってくれたら…という想いを込めて、
親しみやすいひらがな4文字のネーミングにすることを決めました。

―オリジナルの香りはどのようにして生まれるのでしょうか。
島田の景色からインスピレーションが湧きあがってきます。
一番大切にしているのは、風景を「色」で表現すること。
柑橘のオレンジ色、清らかな水のブルー…。素材から考えることももちろんありますが、
主にその景色を色で例えていくところから香りが生まれます。
島田の風景って、本当にきれいなんです!
長らく東京や都会での生活を送ってきましたが、あらためて地元島田に帰ったら…。
夕日が、空が、稲穂が風にそよいでいるのが、こんなにきれいだったっけ!って。
都会ではビルの隙間に見えていた夕日も、こちらでは山に沈みゆくところまで見送ることができる。
そんな美しい島田に来てほしい、島田を知ってほしい!という気持ちが私の根底にはあるんですよね。

―その想いが香りやネーミングに反映されているんですね。希代さんが最初にアロマと出会ったのはどんなタイミングだったんでしょう?
大学時代に街づくりやマーケティングについて学んだことから、地域デザインに携わる仕事をしていました。
それから夫の転勤で関西に移り住み、初めての子育てに奮闘する中で、
子どもと肌で触れ合うベビーマッサージをきっかけに、香りやアロマの存在を知りました。
ただ、自分が好きな香りでも子どもには向かなかったり、状態によって感じ方が違ったり。
そうした体験を経て、効能的なものも含めてアロマを学びたいと思ったのがその頃です。
―「銀の山」」では、商品だけでなく「アロマ空間デザイン」も提供されていますね。
10年ほど前からはアロマ空間デザインの仕事を始め、これまでに東京都内の商業施設やスポーツクラブ、
ホテルなどに、アロマで空間のコーディネーションする仕事をしてきました。
その仕事をしながらも、なぜか思い出すのは幼い頃に祖父と出かけた山のこと。
荒れ行く島田の山のことが、次第に脳裏から離れなくなっていって…。
それで、自らの手で「香りをつくる」側としての勉強を始め、約3年前に地元島田に戻り開業しました。

―地元の方のご協力もあって、島田の廃材などをアロマの原料にされていると聞きました。
ありがたいことに、農家や材木店といった多くの方々に廃棄予定の素材をご提供いただいています。
ただ、サステナブルやSDGsとは言うものの、山で採れた木や取り置いていただいた
ミカンを車で運べばガソリンも、加工する際には、ガスも電気も使っています。
本当の意味で環境に優しいとするには、まだまだ課題もたくさんあります。
でも、この地域の資源を生かしていきたい。
そこから、いい香りだねって言ってもらえるものが生まれていくのは、やはり一番の喜びなんです。

―完成した香りについて、周りの方々の反応は?
ご高齢の農家さんだと、「俺、香水は使わないな~」「どうやって使うの?」と、
ちょっと困っていらっしゃることも (笑)。
ただ、“島田の逸品”に認定していただいたことで、
ご年配の方にもアロマが少し身近になってきた気もしています。
先日、「うちは『ほのぼの』使ってるよ~」と
ご高齢の方に言っていただけたときには、もう本当に嬉しくて!
アロマって敷居が高いと思われがちですが、元気になったりリラックスできたりと、
もっと、日々の中にあるものであればと思っています。

―これからどんな香りが生まれていくのか、とても楽しみです。
柑橘の中でも「スルガエレガント」は、静岡を表現する香りとして活用していきたいと考えています。
そして、「銀の山」のアロマがその土地を知ってもらうきっかけになったり、
人と人、土地をつなぐ役割になったりして、最終的には島田や静岡の街づくりにも
生かすことができたら…って思います。
ライター:左藤緋美
静岡市駿河区に本社を構える「栗田産業」は創業130年余りの歴史をもつ鋳物(いもの)メーカー。
ロボットや工業製品に使用される鋳物製品にとどまらず、ビアグラスや箸置きなどを扱う自社ブランドを
立ち上げた取締役副社長の栗田圭さんに、ものづくりや静岡への想いをお聞きしました。
―鋳物のぐい呑みなどを扱う自社ブランド「重太郎」は、なぜ生まれたのでしょうか。
そもそも「鋳物」って聞きなじみがないですよね。金属を型に流し込み成形して作る
金属製品のことなんですが、ロボットや工業製品など多くのものに使われているにも
かかわらず認知度が非常に低い。本来は身近なはずが、
遠い存在になってしまっているんですね。
―鋳物自体の認知度を上げるために自社ブランドを?
それだけではありません。当社が出荷した工業製品は産業用ロボットになり、
それが海外に渡って、世界有数のメーカーで電気自動車を作る。
グローバルに社会貢献をしている一方で、自分や社員が住む静岡には
まったく貢献できていないんじゃないかと…。
そこで今から7年ほど前、一般の方に向けた自社ブランドを立ち上げ、
生活にまつわる商品の製造販売をスタートさせました。
創業者の高祖父がそうであったように、静岡の鋳物産業の発展に貢献したい。
創業者の名「重太郎」と「しずおか鋳物」を冠したのには、そんな想いもあります。

―地元のホビーメーカー「タミヤ」とコラボした “ミニ四駆の箸置き” には驚きました!
何か静岡らしくて面白いものを作ってみたい、独立してそれと分かる形のものはないかと考えたときに、
タミヤさんのミニ四駆が浮かびました。プラモデル好きという私の趣味が
影響している可能性もありますが…(笑)。
そこから、ホビーの町・静岡を象徴するタミヤさんと一緒に“静岡を盛り上げていきましょう!”と、
構想から約2年半をかけ、ミニ四駆の箸置きが誕生しました。
ご覧になった方によるSNSでの拡散やタミヤさんでの販売もあって話題となり、
購入時に「子ども時代に遊んでいた車種を20年ぶりに見て懐かしくて」「昔こうやって遊んでいました」
なんてコメントをくださる方も多くて…。本当に嬉しかったですし、
私も社員も、いつもと違った喜びとやりがいを感じることができました。

―「重太郎」の商品は、日々の生活の中で使える身近なものが多いですね。
少しでも鋳物を身近に感じていただきたいのと同時に、静岡の良さをより引き出せるものは何か?
という視点も大切にしています。
静岡は「吟醸王国」と呼ばれるほど酒蔵も多く、またクラフトビールの生産量は日本でも上位を占めます。
もちろん主役は美味しいお酒や食材で、「重太郎」のぐい呑みやビアグラスはあくまでその良さを引き出し、
引き立てるための道具。「重太郎」の商品がお役に立てるシーンがあれば嬉しい、その一心ですね。

―ほとんどの商品に錫(すず)を使用されていますが?
錫(すず)という金属の作用によって、お酒がまろやかに変化するんですよ。
個人的にはお酒よりお茶のほうが、味わいの変化をダイレクトに感じます。
飲み比べると分かるんですが、本当にうまみや余韻が変わる!
これはぜひ皆さんにも体験していただきたいですね。

―本社をリノベーションし、今年1月に「工房併設のショールーム」としてオープンされました。モダンな店構えも特徴的ですね。
築80年の古民家を生かし、日本の良さを引き出しつつ現代風にアップデートした建物にしたくて。
工房併設という点も重視しました。「重太郎」のぐい呑みは5,000円台と、決して安くはない価格です。
ただ、物の価値は値段だけではないと思うんですね。
太古から続く製法で、職人が手間ひまかけて丁寧に形にしていく様を間近で見て、触れる。
それで初めて価値として認めていただけるのかなと思いますし、
“ものを作る面白さ”をあらためて感じる「体験の場」にもしたい。
そう考えて、ワークショップも可能な工房併設の形を採りました。
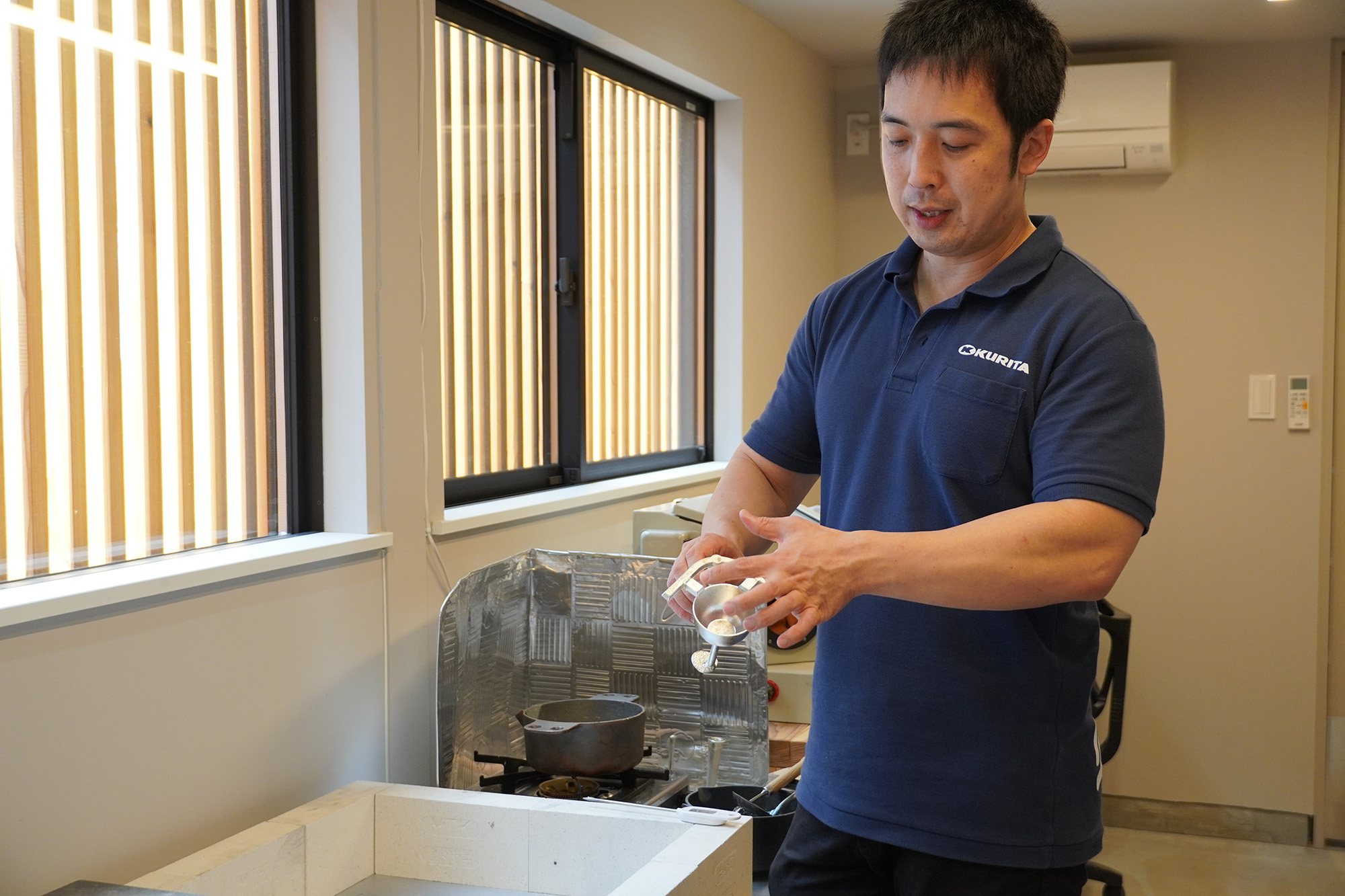
―鋳物の体験は本当に貴重だと感じます。ぜひ今後の構想についても教えてください。
鋳物って、ミニ四駆から工業製品のロボットまで本当に振り幅があって面白いんですよ!
だから今後も鋳物の可能性を広げていきたい。そして静岡のことももっと盛り上げていきたい。
例えば鋳物を使ったお酒やお茶の試飲会などの体験を通じて、静岡と鋳物の両方の良さを
伝えることができると思うんです。
「静岡の鋳物屋」だからこそ持てる何かで、静岡を盛りあげたいという同志の方々と
この先もいろいろな可能性を探っていきたいですね。

ライター:左藤緋美
本日は静岡市葵区東静岡にある物件を紹介します。
こちらの物件はJR「東静岡駅」徒歩1分、静岡鉄道「長沼駅」から徒歩7分のところにある
防災対策も安心!お出かけにも便利な立地にある分譲賃貸マンションです!
\こんな移住希望者にお勧め/
☑車がなくても困らない、生活に便利な場所で暮らしたい!
☑防災対策やセキュリティがしっかりとした住まいに暮らしたい!
☑程よく都会の場所に移住したい!
本日紹介する物件は静岡市葵区東静岡というエリアがあり
徒歩圏内に銀行やクリニック、また「MARK IS 静岡」という
大型商業施設もある為、車を持っていなくても
快適に生活を送ることができるエリアとなっています。

また近くには「東静岡 天然温泉 柚木の郷」という人気施設があり、
温泉をはじめ、岩盤浴や今話題のサウナなどを楽しめることができます!
本や漫画、食事なども楽しめるスペースもあるため、
休日は1日中過ごすことができそうですね♪
それではさっそく物件の紹介にうつっていきましょう!
こちらの物件は防犯対応型の免震マンションとなっており、
1人で移住される方も安心して暮らすことができるマンションです。
リビングダイニングは約17.3帖と広々としたスペースとなっております!
友達をお家に呼びながら移住ライフを楽しむことができそうです♪

キッチンはディスポーザー付なので、お料理のあとの片付けも楽ちん♪

浴室暖房も完備しているお風呂は、冬でもゆったり自分時間を過ごすことができます。

災害が多い近年ですが、災害対策が十分な住まいで安心して
移住ライフを送ってみてはいかがでしょうか?
さまざまな地域を巡りながら自分にぴったりな土地と住まいを見つけてみてくださいね!
本日は静岡市葵区にある物件を紹介します。
こちらの物件はJR「静岡駅」徒歩6分、静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩2分のところにある賃貸物件で、
先日ご紹介した『【賃貸】人を呼びたくなる!ブルックリンスタイルの街中おしゃれ物件(https://shizuoka-iju.jp/bukken44/)』と同じ賃貸マンションの別のお部屋をご紹介させて頂きます!
ポイントはなんといっても、アダストリア・ライフスタイル・クリエイションが
内装プロデュースを行い、新静岡セノバの出店テナントである「niko and …」の
エッセンスを施してお部屋になっていること!
\こんな移住希望者にお勧め/
☑家具や内装にこだわりたい!
☑駅の近くや利便性の良い場所に移住したい!
☑初期費用を押さえて移住したい!
本物件の近くには商業施設「新静岡セノバ」を始め、スーパー、コンビニ、飲食店があり、
新静岡セノバには静岡鉄道の始点となる駅「新静岡駅」を始め、
バスターミナルや、タクシーの停留所もあるため大変利便性の高い立地となっております!
また今回入居者には、新静岡セノバ「niko and …」で税込11万円分の家具を
ご購入いただける特典のプレゼントがあるとのこと!
初期費用を押さえて移住を検討している方は必見です!
室内は「niko and …」の店舗の内装をイメージした床材・壁材をお部屋に合わせてセレクト!
移住後の新生活がわくわくするような内装デザインとなっております!
思わず人を呼びたくなってしまうようなお洒落なお部屋ですね。

家具については入居特典をご利用いただけば、
近隣の商業施設、新静岡セノバ「niko and …」にて、
内装にもマッチするお好きな家具をお選びいただけます。
ぜひ自分好みのお部屋にアレンジしてみてくださいね!
キッチンや洗面所にもおしゃれなこだわりが!
タイルを基調としたスペースとなっております!

写真を見ているだけで移住後の生活が楽しみになってきますね!
静岡で自分好みの暮らしを実現してみませんか?
何かご不安な点ご不明点等ございましたら、静岡移住計画までお問合せください!
(※1)入居者特典について
入居特典をご利用いただけば、近隣の商業施設、新静岡セノバ「niko and …」にて、
内装にもマッチするお好きな家具をお選びいただけます。
・ご利用可能額/110,000 円(税込)
・対象商品/新静岡セノバ「niko and …」内の家具・雑貨等
・家具購入期限/入居日より半年間
その他、詳細はご契約時にお知らせいたします
(※2)アダストリア・ライフスタイル・クリエイションについて
アダストリアの持つ多様なノウハウやリソースを活かし、
企業さまと一緒に新たなビジネスを生み出し、様々なワクワクをつくるプロデュース集団です。
アダストリアグループブランドとのコラボレーションや、企業さまの事業支援など、
「なんかできない?」というざっくりとした相談からお聞きします。
WEBサイト http://alc.adastria.co.jp/
(※3)niko and …について
niko and … は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。
実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、
意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。
そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。
142店舗展開(2023年3月末時点、WEBストアを含む)。
<公式WEBストア .st(ドットエスティ) > http://www.dot-st.com/nikoand/
<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp
<Instagram>https://www.instagram.com/nikoand_official/
(※4)株式会社アダストリアについて
株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、
「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、
グループで 30を超えるブランドを国内外で約1,400店舗展開する
カジュアルファッション専門店チェーンです。
2023 年に創業 70 周年を迎え、「Play fashion!」のミッションのもと、
人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す
“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。
<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 21 番 1 号渋谷ヒカリエ
<URL> https://www.adastria.co.jp/
